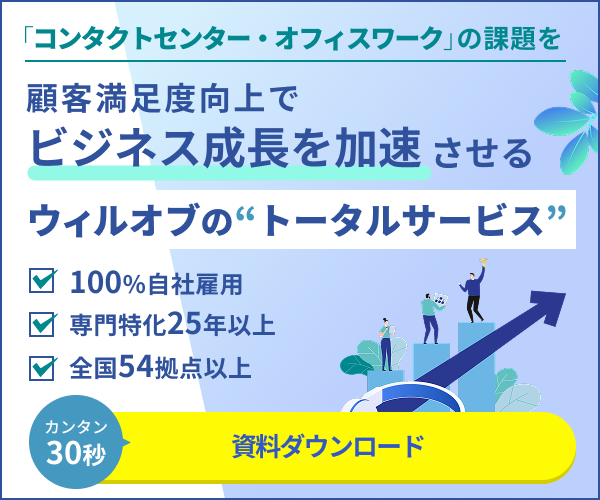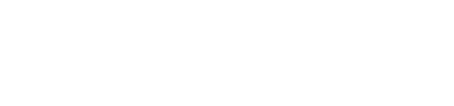コストセンターからプロフィットセンターへ│メリットと実践ステップを徹底解説
2025/11/05
- 従業員満足度向上
- 生産性向上
- 顧客満足度向上

コールセンターの業務は「コスト」として扱われがちですが、近年では“収益を生み出す部門”として再評価する動きが広がっています。売上に直結する業務へと進化させることで、企業全体の価値向上にもつながります。
本稿では、コールセンターをプロフィットセンターへと変革するために必要な考え方や具体的なステップ、注意点を体系的に解説します。経営者・マネージャー・現場担当者の皆様にお役に立てれば幸いです。
本稿でわかること
- プロフィットセンターとコストセンターの違いと、それぞれの役割
- プロフィットセンター化によって得られるメリット
- KPI再設計や経営層への提案を含む、プロフィットセンター化の手順
- 他部門との連携や目標設計で注意すべき落とし穴と対策について
プロフィットセンターとは?コストセンターとの違い
本章では、まず「プロフィットセンター」という概念と、その対比として「コストセンター」について解説します。
プロフィットセンターとは何か?
プロフィットセンターとは、収益(売上)と費用の両方を管理し、「利益」を基準に評価される部門のことです。営業部門や販売部門が代表的で、企業の売上拡大や成長を牽引する中心的な役割を担います。目的は明確に「利益を生み出すこと」にあり、戦略的な意思決定の主体ともなるでしょう。
コストセンターとの違い
一方、コストセンターは収益には直接関与せず、業務の効率化や品質維持を主な目的とする部門です。例えば、管理部門や総務部門、あるいは従来型のコールセンターなどがこれにあたります。これらの部門は、企業全体の運営を支える役割を担いながらも、利益の創出には直接的に寄与しないため、評価軸は主にコスト削減や処理件数となるのが一般的です。 以下の表に、プロフィットセンターとコストセンターの違いを整理しました。
| プロフィットセンター | コストセンター | |
| 目的 | 利益を生み出すこと | 業務効率化・品質維持 |
| 評価指標 | 利益 | コスト削減、処理件数 |
| 売上への関与 | 直接的 | 間接的 |
| 部門例 | 営業部門、販売部門 | 総務部門、管理部門など |
プロフィットセンター化のメリット
ここでは、企業がプロフィットセンター化を進めることで得られる具体的なメリットについて説明します。単なる評価制度の変更ではなく、組織全体の成長戦略や顧客満足度、従業員満足度にも深く関係する重要な取り組みです。
売上向上
顧客対応を「売上に直結する業務」として再設計することで、アップセルの提案や解約防止策が実行され、LTV(顧客生涯価値)の最大化が可能になります。顧客接点が利益につながる構造を明確にすることが、企業にとって大きな強みとなるでしょう。
リピート購入の促進・企業イメージの向上
一貫性のある丁寧な対応を継続することで、CS(顧客満足度)は向上し、自然とリピート購入や好意的な口コミが広がります。さらに、応対品質の高さが企業ブランドへの信頼に直結し、他社との差別化にもつながります。
サービス品質の向上によるクレームや解約率低下
「売上に貢献する部門」としての意識が現場に浸透すれば、改善活動へのモチベーションも高まります。その結果、サービス品質が向上し、クレームの減少や解約率の低下といった成果も得られます。
従業員満足度(ES)やモチベーション向上
プロフィットセンターとしての認識が従業員の自信や誇りにつながり、ES(従業員満足度)も向上します。自身の仕事が会社に貢献しているという実感が、離職率の低下や、生産性向上にも貢献するでしょう。
投資価値の可視化(経営層への説得材料)
売上や顧客貢献が可視化されることで、システム投資や人員増強の正当性を経営層に訴えやすくなります。これにより、企業資源の戦略的な配分が可能になり、持続的な成長が見込めます。
プロフィットセンター化に向けたステップを紹介
それでは、プロフィットセンター化を進めたい企業様にむけて、効果的なステップをご紹介します。単なる制度導入ではなく、実行可能かつ持続可能なフレームワークを構築するためのヒントをお届けします。
目的と目標の明確化
最初のステップは、「なぜプロフィットセンター化を図るのか」という目的を言語化することです。売上貢献の可視化なのか、経営層の理解を得たいのか、目的によって戦略もKPIも異なります。曖昧な目的では、社内の協力体制も得にくくなるため、注意が必要です。
現状のKPIを再定義する
処理件数や応答率といった従来の指標だけでは、売上貢献の評価はできません。LTVや解約率、アップセル率など、より本質的な「成果」に基づいたKPIを設定することで、現場の意識も変わっていくでしょう。
実践している他社のベンチマーク
他社事例の活用は、自社にとって有効な施策を選別する上で非常に有益です。特にNPSや定期的な契約更新率をKPIに取り入れる業界の事例は、コールセンターや顧客対応部門のプロフィットセンター化において有用なモデルとなります。
経営層への説明ロジックを明確化
プロフィットセンター化の実現には、経営層の理解と支援が不可欠です。そのためには、「どのように売上に貢献するのか?」を論理的かつ実証的に説明できる構造が求められます。
単なるKPIの数値だけでなく、以下の要素を組み合わせた多角的なアプローチが効果的です。
- 定量データ:導入前後の売上変化、LTVの上昇、解約率の改善など
- 定性情報:現場スタッフの声、顧客の反応、業務フローの変化
- 比較資料:他社事例との比較、ベンチマークデータの提示
- 投資対効果の提示:システム投資や教育費用に対する利益改善の試算
プロフィットセンター化を進める上での落とし穴・注意点
プロフィットセンター化は企業の利益体質を強化する有効な施策ですが、進め方を誤ると逆効果になりかねません。ここでは、実際の導入現場で起こりやすい落とし穴を詳しく解説し、それぞれに対する具体的な対策を示します。
無理な売上目標設定による現場負荷
プロフィットセンター化を急ぐあまり、従来の業務設計を無視した過剰な売上目標を設定してしまうケースが散見されます。特に、受動的業務が中心だったコールセンターにおいて「アップセル必須」「解約阻止率〇%達成」などの過大なノルマを課すと、以下のような副作用が発生します。
- 応対品質の低下(CS悪化)
- マニュアル重視による画一対応化
- ストレス増大による離職者の増加
- 過剰な数字偏重によりクレームが増加
このような事態を防ぐためには、「現場がコントロール可能なKPI」を設計することが重要です。例えば、単にアップセル件数を追うのではなく、「アップセル提案率(提案行為の頻度)」や「LTV改善に貢献した件数」など、行動ベースで評価できる指標へ転換することで、モチベーションと成果の両立が可能になります。
他部門との連携不足による孤立化
プロフィットセンター化において最も見落とされがちなのが、「センター単体では売上を作れない」という構造的な現実です。売上の最大化には、商品・価格設計を行うマーケティング部門、販売活動を行う営業部門、さらにはシステム部門の支援が不可欠です。
以下のような連携不足は、センターの孤立を招き、プロフィットセンター化を妨げます。
- 顧客対応履歴と営業データの未連携
- CRMや分析ツールが他部門と分断
- キャンペーン内容が現場に共有されない
- 部門間でKPIが一致していない
これらを回避するには、「施策企画の初期段階から多部門を巻き込む」ことが重要です。現場のKPIと経営戦略が一致するよう、共通の目標設定とデータ連携の仕組みを整備しなければなりません。
プロフィットセンターについてのまとめ
本記事では、コールセンターなどの部門をプロフィットセンターとして再構築するためのポイントを解説してきました。重要なのは、「売上貢献の可視化」と「社内理解の獲得」を並行して進めることです。まずは目的を明確にし、KPIの見直しから始めてみましょう。CSやESの改善がやがて収益に反映される構造を作ることで、コールセンターは“守り”から“攻め”の部門へと生まれ変わるでしょう。
コンタクトセンターの運営課題をお持ちのご担当者様へ
「コンタクトセンターの人材採用がなかなかうまくいかない」「定着率をあげたい」「生産性を高めたい」とお悩みのご担当者様、まずはお気軽にウィルオブ・ワークにご相談ください。コールセンター専門特化25年以上、実績多数のウィルオブ・ワークが、お客様の運営課題にカスタマイズのご提案をさせていただきます。ご相談・お見積りは無料!下記ボタンよりお気軽にご相談ください。
Writer編集者情報
-

コネナビ編集部 平井 美穂
2012年、株式会社セントメディア(現:株式会社ウィルオブ・ワーク)へ入社。
コールセンターとオフィスワーク領域に特化した人材サービスに従事し、カスタマーサポートをはじめ、営業やキャリアアドバイザーなど幅広い職務を経験。
現場で培ったCS対応力と人材支援の知見を軸に、採用や運営における課題解決を支援。
2022年からは、コンタクトセンター業界の情報サイト「コネナビ」編集部の責任者として、業界の課題に寄り添う情報発信を推進。
企業向けメディア「コネナビ」と求職者向けメディア「コネワク」を通じて、ユーザーの課題解決と業界の成長に貢献することを目指している。
趣味: 森林浴、神社巡り、アートに触れること
特技: 細かい点に気づくこと
Related article関連記事
関連記事がありません。