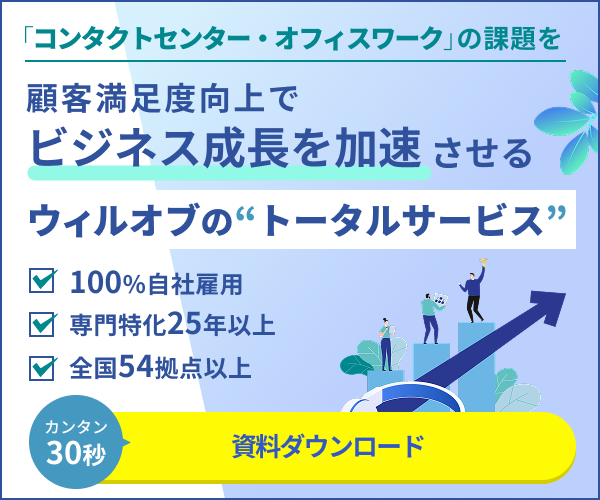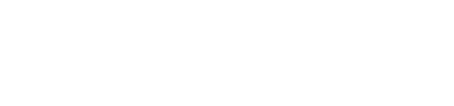事務効率化の進め方│属人化解消と効果的な施策の選び方を解説
2025/09/01
- アウトソーシング
- コスト削減
- システム導入
- 従業員満足度向上
- 業務効率化
- 生産性向上
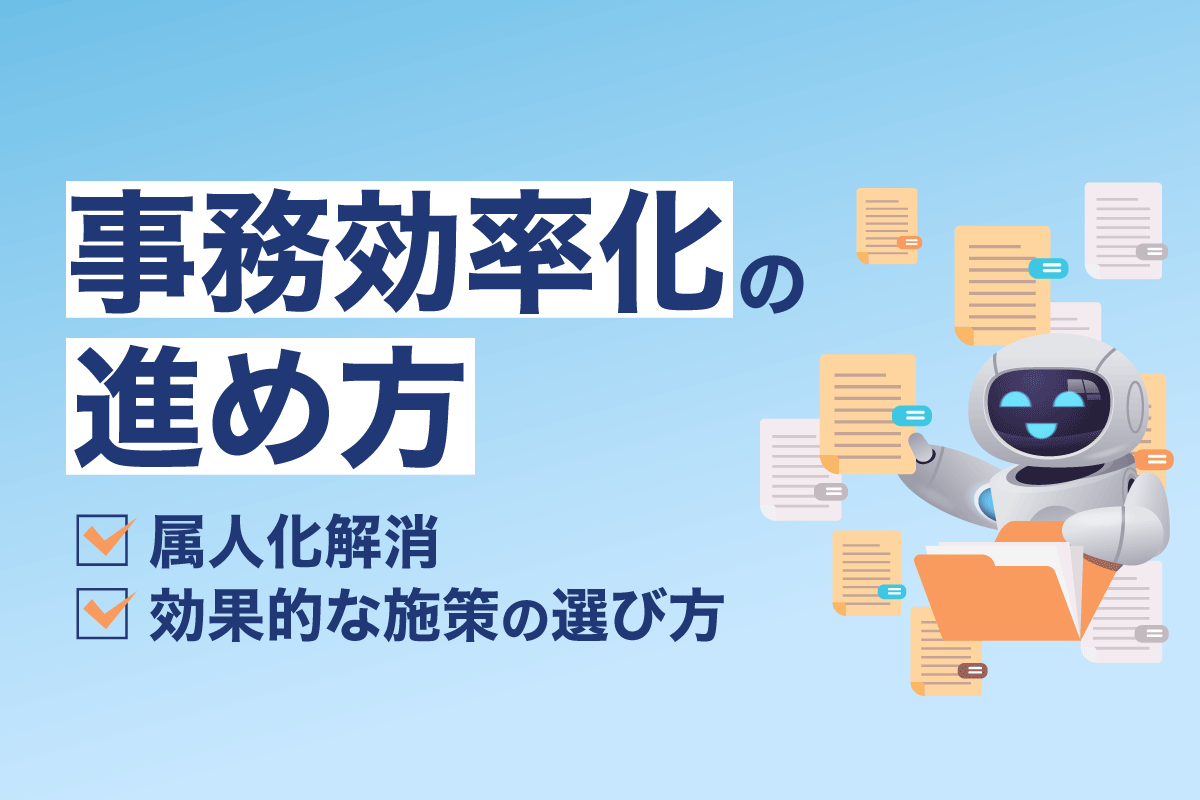
DX推進が進む中でも、まだ具体的な事務効率化に着手できていない企業は少なくありません。
「特定の人にしか対応できない業務がある」「日常業務に追われ効率化が後回しになっている」と悩む企業責任者も多いでしょう。
本記事では、事務効率化を進めるための基本的な考え方から、実行ステップ、自社に合った施策の選び方、さらに個人レベルで活用できる工夫までを解説します。ぜひ自社の課題解決の参考にしてください。
属人的な業務から脱却し、事務効率化をスムーズに進めたいとお考えの方は、ウィルオブ・ワークにご相談ください。
当社は、RPA導入支援サービスやBPOアウトソーシングサービスを通じて、企業ごとの課題に合わせた最適なソリューションを提供しています。
「業務に追われ改善が進まない」「効率化を進めたいが何から始めればいいか分からない」といったお悩みも、専門のコンサルタントがサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。
事務効率化とは
事務効率化とは、日々のバックオフィス業務や定型的な事務作業におけるムダ・ムリ・ムラを取り除き、生産性を高める取り組みを指します。単に作業を早く終わらせることではなく、業務フローを見直し、ツールの導入や分業体制の整備などを通じて組織全体の業務を最適化することが目的です。
なぜ今、事務効率化が必要なのか
近年、事務効率化が重視される背景には、次のような3つの要因があります。
人手不足の深刻化
少子高齢化により労働人口が減少しており、限られた人員で業務を回す必要があります。担当者一人あたりの負荷が高まる中で、ムダを減らし処理能力を引き上げる取り組みが欠かせません。
DX推進の加速
近年、日本ではデジタル・トランスフォーメーション(DX)の必要性が急速に高まっています。特に、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」では、老朽化した基幹システムを放置した場合、2025年以降に最大12兆円規模の経済損失が生じるリスクが指摘され、「2025年の崖」問題として広く認知されました。この警鐘を受けて、多くの企業がシステム刷新や業務のデジタル化、データ管理の見直しに積極的に取り組むようになっています。
さらに、新型コロナウイルスの流行により、テレワークや非対面業務への移行が急速に進みました。従来の紙や押印に依存した業務ではリモート対応や意思決定スピードに限界があり、事務作業のデジタル化・標準化の必要性が改めて浮き彫りになっています。
DX推進は多くの企業にとって「待ったなし」の経営課題となっています。
コスト削減と収益性向上の圧力
限られたリソースで成果を出すことが求められる中、定型作業の時間や手戻りを減らすことは直接的なコスト削減につながります。効率化は利益体質の強化に直結します。
このように、事務効率化は「現場の働きやすさ」を高めるだけではなく、企業の競争力や収益性を左右する経営課題として位置づけられます。
取り組むことで得られるメリット
事務効率化を進めることで、企業は次のようなメリットを得られます。
業務コストの削減
作業時間の短縮や人員配置の最適化により、残業代や人件費を抑えられます。
生産性の向上
定型業務の負担が減ることで、社員が本来取り組むべき企画や業務改善に集中できるようになります。
従業員満足度の向上
単純作業や二重業務が減ることで社員のストレスが軽減し、働きやすい環境につながります。
顧客対応力の強化
バックオフィスがスムーズになると、顧客へのレスポンスも速くなり、サービス品質向上に直結します。
DX推進の基盤づくり
業務が標準化・データ化されることで、AIやRPAなど次のデジタル施策を導入しやすくなります。
事務業務の課題
定型作業や紙文化の残存
事務業務には、データ入力・帳票作成・請求処理・承認フローなど、毎日繰り返される定型作業が数多く存在します。これらは本来自動化や簡素化が可能な領域でありながら、依然として人手に頼っているケースが少なくありません。
さらに、紙の書類や押印文化が残っている場合、印刷・押印・郵送・保管といったプロセスが追加され、時間とコストの大きなロスにつながります。特にテレワークやリモート体制下では、紙文化が業務のボトルネックとなりやすい点が大きな課題です。
属人化と情報共有不足
「その業務は特定の社員しか対応できない」という状況は、事務業務でよく発生します。長年の経験や個人の判断に依存した業務は、マニュアル化や引き継ぎが不十分なため、属人化が進みやすい傾向があります。
この状態では、担当者が不在のときに業務が停滞するだけでなく、品質のばらつきやミスの増加も招きます。
また、情報共有が不足すると、同じ作業を複数人が重複して行ったり、必要な情報にたどり着くまでに時間がかかったりするため、生産性を著しく低下させてしまいます。
部署間連携の非効率
事務業務は経理・総務・人事・営業サポートなど複数部署にまたがって存在するため、部署間の連携不足が効率低下を招く原因となります。
例えば、申請や承認に複数の部署が関わる場合、書類の回覧や承認待ちが長期化し、業務全体のスピードを阻害します。
また、システムが部門ごとに分断されていると、データの二重入力や情報の整合性確認といった余計な作業が発生し、現場の負担が増加します。結果として、社員は「本来やるべき業務」ではなく「調整や確認作業」に時間を奪われることになりがちです。
事務効率化の進め方
事務効率化は「現状を把握し、改善策を試し、成果を測りながら定着させる」という流れで進めるのが基本です。やみくもにツールを導入するのではなく、段階を踏むことでムダなく着実に進められます。
現状の見える化と課題抽出
まずは自社の事務業務を「どの部署で、誰が、どのくらいの工数で行っているのか」を洗い出すことから始めます。現状を可視化することで、時間がかかっている作業やボトルネックが明らかになります。
- 業務棚卸し:対象業務・担当者・頻度・工数をリスト化
- 数値化:処理時間、件数、承認回数、エラー率などを計測
- ボトルネック特定:紙・押印、転記、承認待ちなど停滞ポイントを確認
- 優先順位付け:「効果が大きく、実現が容易」な業務から着手
改善施策の設計と実行
課題が整理できたら、改善策を具体的に設計し実行します。改善は「業務の簡素化」「デジタル化・自動化」「役割や体制の見直し」の3方向で進められます。
- プロセス簡素化:不要な手順の削除、承認者数の削減
- 自動化・デジタル化:RPAやワークフロー、クラウド文書管理の導入
- 役割再設計・外部活用:業務の分担見直しやアウトソーシングの活用
実行する際は、まずは小規模でテスト導入し、効果を確認しながら全社に広げるのが失敗しないコツです。現場への説明やマニュアル作成など、浸透に向けた工夫も欠かせません。
効果検証と定着化
施策を実施したら、効果を数値で測定し、必要に応じて改善を加えます。そのうえで新しいやり方を標準化し、社内に定着させていくことが重要です。
- KPI比較:処理時間・エラー率・残業時間などのBefore/Afterを確認
- 是正と標準化:課題が残る場合は改善を追加し、作業手順書を更新
- 定着・横展開:定期的に振り返りを行い、他部署や類似業務へ展開
この「検証と定着」まで行うことで、効率化が一時的な取り組みではなく、組織文化として根付いていきます。
こうした流れで進めれば、業務効率化を「やって終わり」ではなく「成果が出続ける仕組み」にできるでしょう。
事務効率化の具体策
事務効率化の方法は「仕組み」と「人」の両面から進めることが重要です。具体的には次の4つに大別できます。
- ツールの導入(RPA・ワークフロー・クラウド活用)
- 業務プロセスの見直し(承認フロー・マニュアル化)
- アウトソーシングの活用
- 個人の工夫(整理整頓・タスク管理・PCスキル)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ツール導入(RPA・ワークフロー・クラウド活用)
ツールは事務効率化を大きく加速させる手段です。特に定型業務はシステム化によって大幅に工数削減できるため、まず検討すべき領域といえます。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)
RPAは、人がパソコン上で行う定型作業を、ソフトウェアが代わりに実行できるツールです。
例えば、Excelからシステムへデータを転記する、請求書を自動作成して送付する、Webサイトから必要な情報を取得するといった作業を自動化できます。人の手を介さず24時間稼働できるため、作業時間を大幅に短縮し、ヒューマンエラーも防ぎます。
ワークフローシステム
ワークフローシステムは「申請や承認の流れをオンライン化し、スムーズに処理できるツール」です。
経費精算や稟議の承認を紙やハンコで回す代わりに、システム上のボタン一つで完結できるようになります。リモートワーク環境でも対応できるため、承認のスピードが格段に上がります。
クラウドサービス
クラウドサービスは「文書やデータをインターネット上に保管・共有できるツール」です。
文書管理やデータベースをクラウド化すれば、社内外どこからでもアクセス可能で、複数人で同時編集もできます。テレワークや拠点が分散している企業でも、情報共有がスムーズに行えます。
業務プロセスの見直し(承認フロー・マニュアル化)
ツールを導入する前に、まずは業務の流れそのものを整理することも重要です。
承認フローの見直し
承認者が多すぎたり、順番が複雑になっていたりすると、無駄な待ち時間が発生します。必要な承認数を最小限にし、並行承認を取り入れることでスピードが改善するでしょう。
マニュアル化
担当者の経験に依存している業務は、マニュアルにまとめることで誰でも対応できるようになります。属人化を防ぎ、引き継ぎや教育の効率も上がります。
アウトソーシングの活用
すべての事務業務を自社で抱える必要はありません。非コア業務を外部に委託することで、社員を本来注力すべき戦略業務へ集中できるようになります。
メリット
- 人手不足の解消:繁忙期や欠員時にも安定した業務遂行が可能。
- コストの最適化:人件費を固定費から変動費にシフトでき、必要なときに必要な分だけ利用できる。
- 品質とスピードの確保:専門人材による対応で、業務の正確性や処理スピードが向上。
- マネジメント負荷の軽減:採用・教育・労務管理といった付随業務を削減できる。
活用しやすい業務例
- ルーチン業務:データ入力、問い合わせ対応、書類整理など毎日繰り返す作業
- 専門性の高い事務:給与計算、社会保険手続き、採用関連業務など、知識や正確性が求められる業務
- 繁忙期対策:決算や採用ピークなど、一定期間だけ業務量が増えるとき
効率化を進めたいのに「手が回らない」と悩む企業にとって、アウトソーシングは即効性があり、かつ安定性も確保できる解決策です。
個人の工夫(整理整頓・タスク管理・PCスキル)
事務効率化はシステムや組織の仕組みだけでなく、社員一人ひとりの工夫にも左右されます。小さな改善の積み重ねが大きな成果となり、組織全体の効率を底上げします。
整理整頓
デスクや共有フォルダが散らかっていると、書類やデータを探すだけで1日に数十分が失われることもあります。整理整頓は単なる「きれいにすること」ではなく、検索や確認にかかる時間を削減する仕組みづくりです。たとえば、フォルダ名やファイル名にルールを設けるだけで、社内全員が同じ基準で情報を探せるようになり、属人化の防止にもつながります。
タスク管理
「急ぎの業務に追われて本来の重要業務が進まない」というのは多くの企業で共通する課題です。タスク管理の目的は優先順位をつけるだけでなく、“緊急ではないが重要な仕事”に時間を割く仕組みをつくることです。具体的には、毎朝の段階で「今日必ず終える3つのタスク」を決めるだけでも、後回しを防ぎ、業務の質が安定します。
PCスキル
ショートカットやExcel関数の習熟は、単に便利というレベルではなく、日常業務の処理能力そのものを底上げする投資です。例えば、関数を組み合わせれば数時間かかる集計を数秒で終えられます。こうした“すぐ効くスキル”をは研修や社内共有で広げることで、効率化の波及効果が一気に高まります。
生成AIの活用
生成AIは、文章作成や情報整理、アイデア出しを支援してくれる「新しい基礎スキル」と言えます。
- 定型文の自動作成:メール文、議事録、社内報告などをAIに下書きさせることで完成までの時間を短縮
- 調査・情報収集:大量の資料や記事を要約させ、必要な情報だけを短時間で把握
- 思考整理・アイデア創出:課題の整理や企画アイデアのブレスト相手として活用
- 学習支援:Excel関数やプログラムコードをAIに聞きながら習得し、即実務に反映
ツール導入や業務プロセス改革とあわせて、個人の工夫や生成AIの活用を組み合わせることで、効率化は一時的な改善ではなく「持続的に成果が出る仕組み」に育ちます。自社課題に適切な施策をぜひ見つけてみてください。
まとめ
事務効率化にはRPAやワークフローなどのツール導入、承認フローの見直し、アウトソーシングや個人の工夫など多様な方法があります。ただし、効果を最大化するには自社の課題を正しく把握し、最適な施策を選び、組み合わせて導入することが重要です。
小さな改善から取り組みを始め、自社に合った仕組みづくりを進めていくことが、持続的な効率化への第一歩となります。本記事が企業ご担当者さまの課題解決の一助となれば幸いです。
「どの業務から改善すればよいかわからない」「効率化に取り組んでいるが成果につながらない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひウィルオブ・ワークにご相談ください。
事務業務の効率化は、自社の課題を正しく把握し、最適な施策を選んで導入することが成功の鍵です。
当社は、RPA導入支援やBPOアウトソーシングなど、企業ごとの状況に合わせた効率化ソリューションを提供しています。専門のコンサルタントが貴社の課題を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案します。
Writer編集者情報
-

コネナビ編集部 平井 美穂
2012年、株式会社セントメディア(現:株式会社ウィルオブ・ワーク)へ入社。
コールセンターとオフィスワーク領域に特化した人材サービスに従事し、カスタマーサポートをはじめ、営業やキャリアアドバイザーなど幅広い職務を経験。
現場で培ったCS対応力と人材支援の知見を軸に、採用や運営における課題解決を支援。
2022年からは、コンタクトセンター業界の情報サイト「コネナビ」編集部の責任者として、業界の課題に寄り添う情報発信を推進。
企業向けメディア「コネナビ」と求職者向けメディア「コネワク」を通じて、ユーザーの課題解決と業界の成長に貢献することを目指している。
趣味: 森林浴、神社巡り、アートに触れること
特技: 細かい点に気づくこと
Related article関連記事
関連記事がありません。