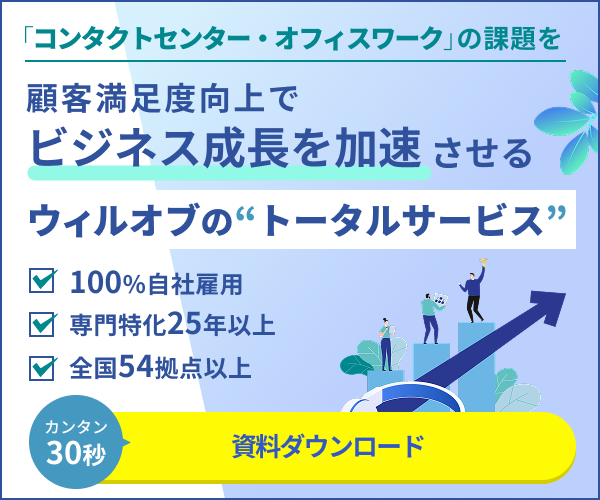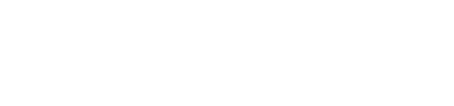感情労働とは?AI時代におけるオペレーターの役割とケア方法を解説
2025/07/25
- 品質向上
- 定着率向上
- 従業員満足度向上
- 教育・育成
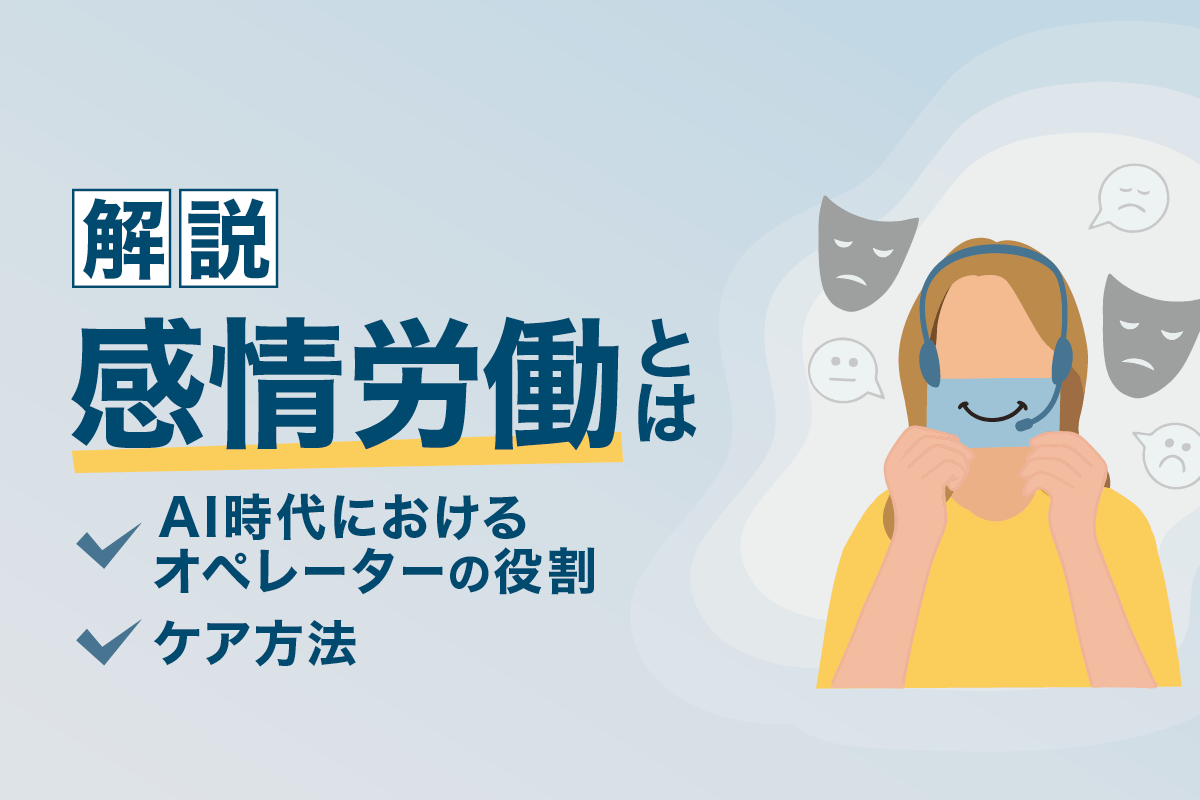
「また一人、優秀なオペレーターが辞めてしまった——」
コールセンターを運営する中で、離職やメンタル不調に悩む管理者は少なくありません。その背景にあるのが、表面化しづらい「感情労働」の負担です。
本稿では、コールセンターにおける感情労働とは何かをわかりやすく解説し、注目されている背景や、コールセンター運営側でできる対策を紹介します。 感情労働の本質を理解することは、職場環境の改善と定着率の向上に直結する重要な視点ですので、ぜひご覧ください。
感情労働とは?
コールセンターで働くスタッフにとって、お客様への対応は単なる作業ではありません。「お客様に寄り添い、傾聴し、落ち着いて、丁寧に、笑声で…」──そう求められる裏には、自分の感情を押し殺し、相手に合わせた反応を続けるという“見えない労働”が存在します。それが「感情労働」です。
この言葉は、アメリカの社会学者アーリー・ラッセル・ホックシールド氏によって提唱されたもので、労働者が「本心とは異なる感情を表現すること」を求められる仕事を指します。
たとえば怒りや苛立ち、不安といった感情を抑え、反対に安心感や親切さを演出する──これはお客様の満足度や信頼感を高めるうえで非常に重要な役割を果たします。
特にコールセンターのように、声や言葉だけで対応する業務では、相手の反応に合わせた「感情の使い方」が成果を大きく左右します。しかしその一方で、こうした感情の調整は目に見えず、評価されづらく、ストレスとして蓄積されやすいという側面があります。
SV(スーパーバイザー)の立場では、オペレーターが常に丁寧に対応している姿が「当たり前」に見えてしまいがちで、その裏にある感情的な負荷に気づきにくい傾向があります。 この「見た目には分からない負担」こそが、感情労働が軽視され、適切に対処されにくくなる大きな要因と言えるでしょう。

感情労働の種類
感情労働は特定の業界だけに見られるものではなく、多くの「対人業務」で発生しています。特に、顧客や患者、子ども、利用者などとのやり取りを通じて、感情のコントロールが求められる職種では、その傾向が顕著です。以下に代表的な感情労働の職種を紹介します。
• コールセンターのオペレーター
顧客からの問い合わせやクレームに対し、常に冷静で丁寧な対応が求められます。電話やチャットといった非対面のコミュニケーション手段では、声のトーンや言葉遣いが印象を大きく左右します。
• 看護師・医師
患者やその家族に対して不安を与えないよう、プロフェッショナルな態度を保つ必要があります。医療現場の緊張感の中でも、安心感と信頼を与える表情や声の使い方が求められる職種です。
• キャビンアテンダント(CA)
飛行中の不安やトラブルの際にも、冷静かつ親しみのある態度を保つことが必要です。国籍や文化の異なる乗客への柔軟な対応も求められます。
• 保育士・教師
子どもの感情に寄り添いながら、自らの感情をコントロールして指導する必要があります。加えて、保護者との対応や、複数の人間関係を同時に調整する場面も多く、感情面の負担が大きい仕事です。
• 介護士・福祉職
利用者の身体的・精神的な支援を行う中で、感情的に不安定な場面にも丁寧に接する姿勢が求められます。感情の共有が信頼関係に直結するため、高度な感情調整力が必要です。 これらの職種に共通しているのは、「感情」が業務の一部であり、成果に大きな影響を与えるという点です。コールセンターもその代表格であり、日々の応対で発生する感情のやり取りは、目には見えなくとも多大なエネルギーを消費しているのです。
感情労働が注目される背景
近年、「感情労働」という言葉があらためて注目されています。その背景には、社会構造や職場環境の変化が関係しており、特にコールセンターの現場では、感情労働の負荷が以前にも増して高まっている傾向が見られます。以下では、その主な要因を4つの視点から解説します。
離職理由の上位に「人間関係・ストレス」がある
多くのコールセンターでは、離職理由として「人間関係がうまくいかない」「感情的に疲れる」といった声が目立ちます。こうした理由は、スキル不足や業務内容の問題ではなく、「感情を抑えて働き続けることによる疲労」が根本にあることも少なくありません。 実際、問題が表面化する頃には、すでにモチベーションの低下や信頼関係の崩壊が進んでいるケースが多く、早期発見が難しいのが実情です。
AI導入で「人が対応すべき案件」が重くなっている
コールセンター業界ではチャットボットの導入が進み、定型的な問い合わせは自動化されています。一見すると業務負担が軽減されたように見えますが、実際には、オペレーターに回ってくる案件の多くが「クレーム対応」や「イレギュラー対応」など、感情的かつ高度な判断を要する案件に偏りがちです。 その結果、「精神的負荷の高い案件ばかりを担当する」という状態に陥りやすく、感情労働の密度は確実に増しているといえます。
管理者が「心のケア」まで求められるようになったこと
以前は、SV(スーパーバイザー)などの管理職には主に数値管理(KPI、稼働率など)が求められていました。しかし現在では、従業員のメンタルケアや感情面のフォローも業務の一環とされています。 特にコールセンターでは、日々のストレスや顧客からの強い言葉が心理的な不調を引き起こすケースが後を絶ちません。そのため、SVには「数字だけでなく心も見る」姿勢が強く求められています。
カスタマーハラスメントの増加
近年、社会問題として注目されている「カスタマーハラスメント(カスハラ)」も、感情労働への注目を高めている重要な要因です。
カスハラとは、顧客から従業員への過剰なクレームや人格否定的な発言、威圧的な要求などを指し、コールセンターはその発生リスクが高い現場です。 声だけのコミュニケーションに依存するため、顧客の怒りや攻撃性がストレートにオペレーターへ届きやすく、対応中の心理的プレッシャーは非常に大きなものとなります。
さらに、「顧客第一」の文化の中では、オペレーターが不当な言動にも我慢を強いられやすく、感情を抑えるストレスが限界を超える原因となります。カスハラの増加は、感情労働の深刻化を加速させる重大なリスクであり、見過ごすことはできず、企業は対策を求められています。
感情労働がもたらすリスクとは
感情労働は、適切にマネジメントされない場合、オペレーター本人だけでなく、職場全体にもさまざまなリスクをもたらします。
ここでは、コールセンターの現場で特に起こりやすい3つのリスクについて紹介します。
笑顔の裏で蓄積する「共感疲労」
お客様に寄り添い、丁寧に対応し続けることは、まさに「共感力」を使い続ける行為です。
しかし、感情を抑えながら共感を演じ続けることで、心がすり減っていく「共感疲労」に陥ることがあります。これは、精神的なバーンアウト(燃え尽き症候群)の一因にもなり得ます。 特にクレーム対応が多い現場では、「また怒られるのではないか」といった不安が積み重なり、業務への恐怖感や拒否反応につながるケースも少なくありません。
離職率の増加
離職理由として「仕事がきつい」「自分には合わなかった」と語られる背景には、感情的な疲労が限界に達していたというケースが多くあります。
気持ちを抑え込み、誰にも相談できないまま、ある日突然退職に至る──これはコールセンターでよく見られる典型的なパターンです。 表面上は何事もないように見えても、「無表情になってきた」「雑談が減った」などの小さなサインを見逃さないことが大切です。
応対品質・顧客満足度への悪影響
感情労働の負荷が限界を超えると、応対品質にも少なからず影響が出てきます。
たとえば、声のトーンが冷たくなる、語尾が強くなる、対応が機械的になるなど、無意識のうちに顧客に“違和感”が伝わってしまいます。 このような状態では、どれほどスクリプトが整っていても、CS(顧客満足度)の維持は困難です。最終的には、個々の対応だけでなく、企業全体のブランドイメージや信頼にも悪影響を及ぼす可能性があります。
感情労働への対策・マネジメント施策とは
感情労働による負担を軽減し、オペレーターが安心して働ける環境をつくるためには、管理者による理解と仕組みづくりが欠かせません。ここでは、現場で今日から実践できる具体的な対策を紹介します。
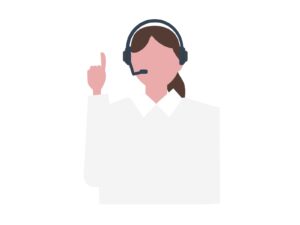
評価されにくい感情労働を「見える化」する工夫
感情労働は、数字として成果が見えにくいため、評価されづらいという問題があります。
まずは、「丁寧な対応をしていた」「感情を抑えて冷静に話していた」など、感情面の努力を具体的に言語化し、フィードバックすることが重要です。 録音データのチェックやモニタリングシートに、感情に関する観点を加えることで、感情労働も明確な評価対象として扱えるようにしましょう。
日報や1on1でできる心のケア
日報や1on1面談を通して、「どんな気持ちで仕事をしているか」を確認する場を設けることも効果的です。
特に1on1では、「あの時、どんな気持ちだった?」といった問いかけにより、感情を自然に言語化する習慣が育まれます。 表面的な業務報告にとどまらず、「感情にも目を向けるマネジメント」を意識することで、ストレスの兆候にも早く気づけるようになります。
新人教育で「感情の扱い方」を教える
新人研修では、業務スキルだけでなく、「感情のマネジメント方法」も伝えることが重要です。
たとえば、
- クレームを受けたときの受け止め方
- 自分を責めすぎない考え方
- 心の切り替え方(深呼吸、席を外すなど)
といった実践的なセルフケアのスキルを教えることで、現場に出てからも冷静に対応しやすくなります。
SV(スーパーバイザー)の役割の見直し
SVは、オペレーターの応対指導だけでなく、精神的なフォロー役としても重要な役割を担っています。
そのため、SV自身が感情労働への理解を深め、共感的なコミュニケーションを意識することが求められます。 また、SVが孤立しないよう、マネージャーと密に連携しながら、チーム全体の感情の状態を把握できる体制づくりも必要です。
AI時代に求められる“人の力”
AIや自動化が進む現代において、「人間にしかできない仕事」が改めて注目されています。感情労働もその一つです。
とりわけコールセンターでは、AIが対応できない場面にこそ、人の価値が発揮されます。
AIではできない「共感」と「安心感」
チャットボットやAI音声認識が 多くの問い合わせに対応できるようになっています。しかし、感情的な相談や複雑なクレームには、人による対応が不可欠です。
たとえば、お客様が怒っていたり困っていたりする場面では、相手の感情を受け止め、安心させる対応が求められます。
AIは情報処理には優れていても、「気持ちに寄り添うこと」は現時点では困難です。 だからこそ、人の“あたたかさ”や“空気を読む力”は、これまで以上に価値あるスキルといえるでしょう。
感情労働はむしろ「強み」になる
感情労働は、単なる「負担」ではありません。適切に評価・サポートすることで、顧客満足度を高める“付加価値”となり得ます。
たとえば、
- 難しい状況でも冷静に対応できる
- 相手の気持ちをくみ取って適切な言葉を選べる
- 緊張感のある場面でも安心感を提供できる
こうしたスキルは、AIには代替できない「人間らしさ」であり、企業のブランドや顧客との信頼構築に直結する強みとなるでしょう。
感情労働のまとめ
感情労働は、コールセンターの現場で起こる最も見えにくく、かつ深刻な労働です。管理者には、その存在を正しく理解し、負担を可視化・ケア・育成の観点から支える役割が求められます。AIの導入が進む今だからこそ、「感情に向き合う力」は人と組織を支える競争力となるでしょう。感情労働をチームの課題ではなく、“武器”としてマネジメントに取り入れることが、これからの職場づくりの鍵となります。
コンタクトセンターの運営課題をお持ちのご担当者様へ
「コンタクトセンターの人材採用がなかなかうまくいかない」「定着率を改善したい」「オペレーターの負担を軽減させたい」とお悩みのご担当者様、まずはお気軽にウィルオブ・ワークにご相談ください。ウィルオブ・ワークは、コールセンター専門特化25年以上のノウハウを活かして、お客様の運営課題にカスタマイズのご提案をさせていただきます。ご相談・お見積りは無料ですので、以下よりお気軽にご相談ください。
Writer編集者情報
-

コネナビ編集部 平井 美穂
2012年、株式会社セントメディア(現:株式会社ウィルオブ・ワーク)へ入社。
コールセンターとオフィスワーク領域に特化した人材サービスに従事し、カスタマーサポートをはじめ、営業やキャリアアドバイザーなど幅広い職務を経験。
現場で培ったCS対応力と人材支援の知見を軸に、採用や運営における課題解決を支援。
2022年からは、コンタクトセンター業界の情報サイト「コネナビ」編集部の責任者として、業界の課題に寄り添う情報発信を推進。
企業向けメディア「コネナビ」と求職者向けメディア「コネワク」を通じて、ユーザーの課題解決と業界の成長に貢献することを目指している。
趣味: 森林浴、神社巡り、アートに触れること
特技: 細かい点に気づくこと
Related article関連記事
関連記事がありません。