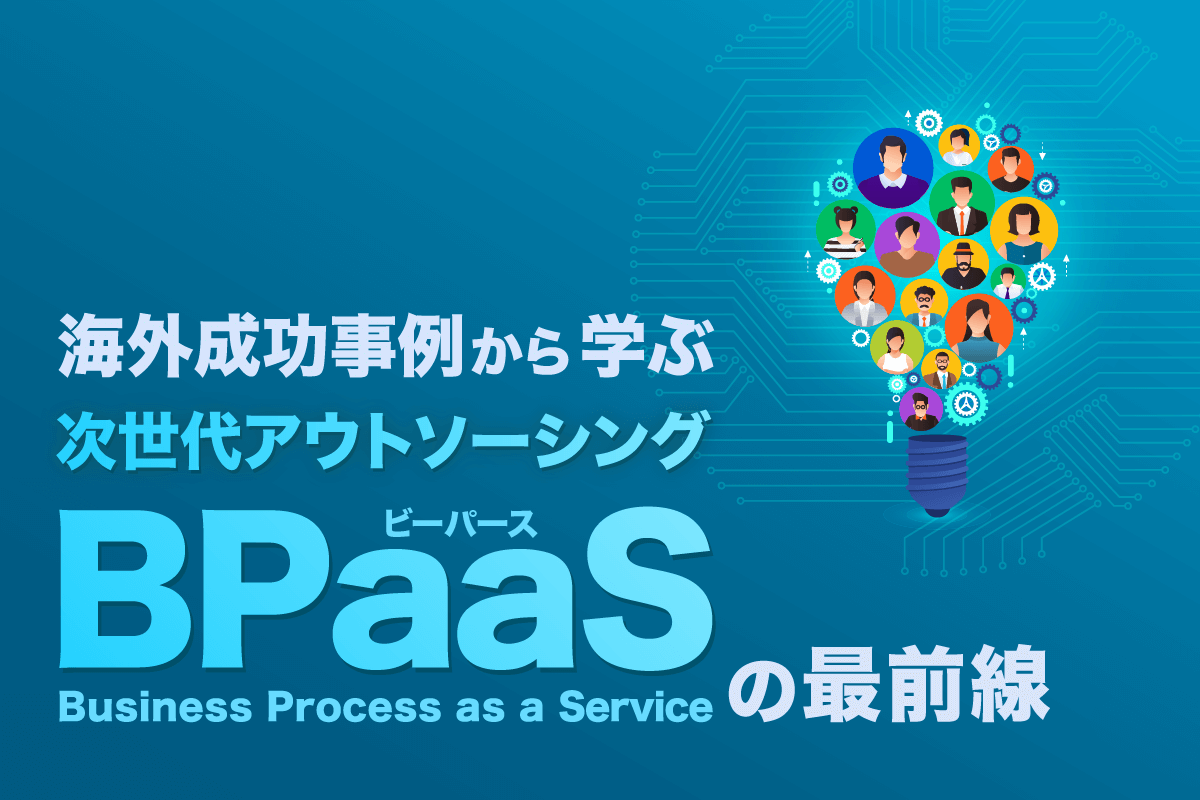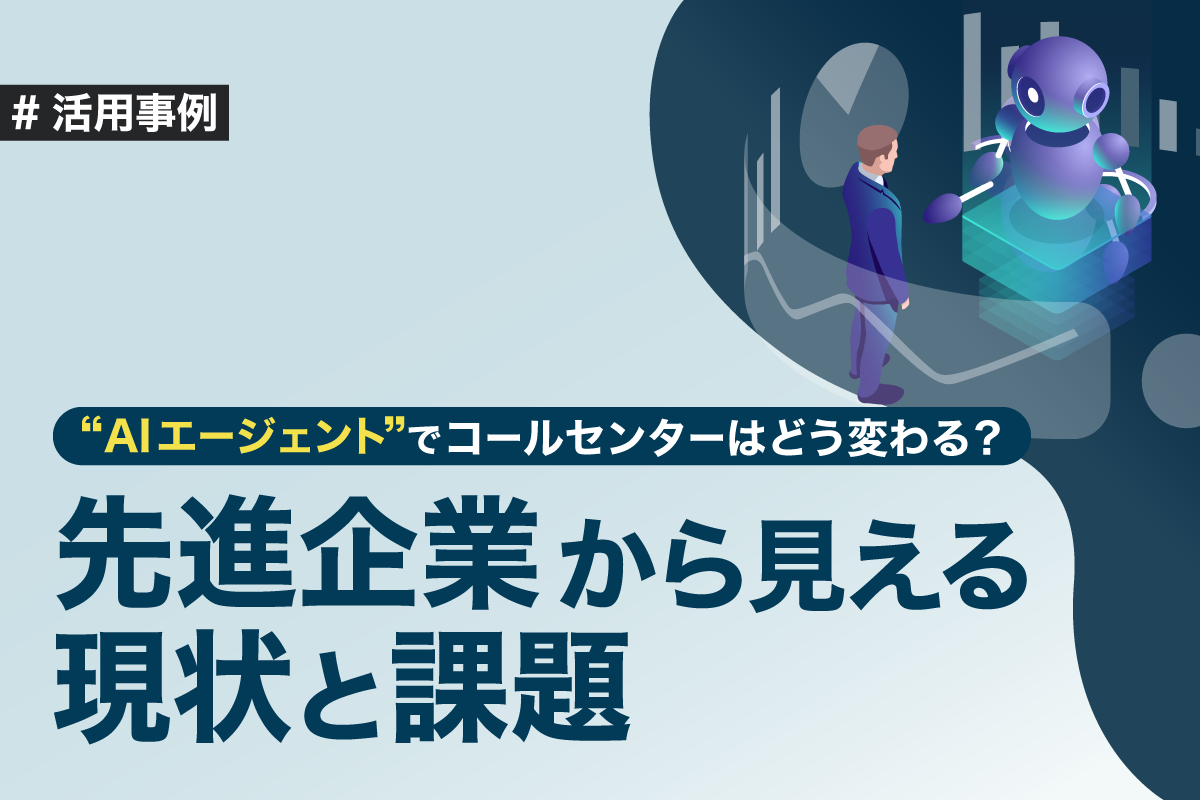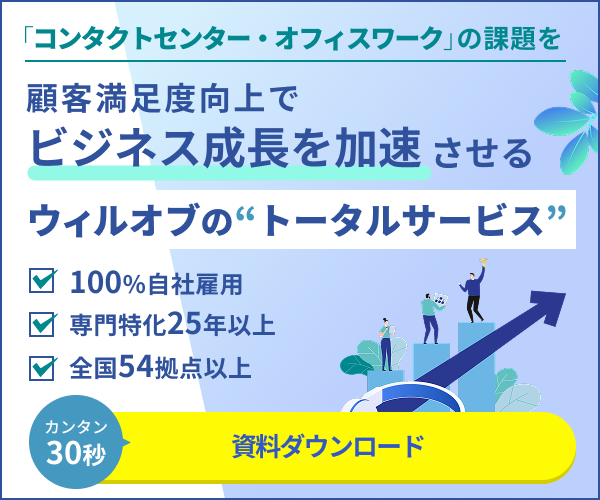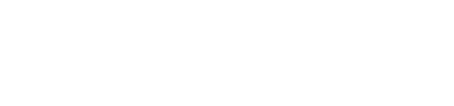【AI最新事例】コールセンター業界を変革する音声AI最前線:技術の進化と具体事例を紹介
2025/09/01
- コスト削減
- システム導入
- 業務効率化
- 生産性向上
- 顧客満足度向上

近年、音声AI(人工知能による音声対話技術)が目覚ましい進化を遂げております。それに伴い、人手に頼ってきた電話対応も、AIを活用した自動音声エージェントによって24時間対応や多言語サポートが現実のものとなりつつあります。
今回は、音声AI分野で注目を集める国内外の企業(ElevenLabs, Kotoba Technologies, J-Moshi, OpenAIなど)を題材に、音声AI技術にフォーカスし、最新の動向を専門的に解説します。それぞれの企業が用いる音声AI技術の概要と進化ポイント、従来技術との差異、具体的な導入事例、今後の技術展望など順に見ていきましょう。
音声AI技術の概要
音声AIとは、人間の「話す・聞く・理解する」能力をAIで再現する技術の総称です。コールセンター向けの音声AIには、大きく分けて音声認識(ASR: Automated Speech Recognition)、音声合成(TTS: Text-to-Speech)、自然言語処理(NLP: Natural Language Processing)、対話制御、そして感情認識・表現 といった要素技術が統合されています。近年の生成AIブームの中で、これらの音声AI技術も飛躍的に進化してきました。
最近の技術の進化例
では、最新の音声AIは従来のモデルと比べて何が優れているのでしょうか?主なポイントを整理します。
リアルタイム性・反応速度の向上
最新の音声AIは処理速度が格段に向上し、ほぼリアルタイムで対話ができます。例えば、後述するKotoba Technologiesの日本語音声認識モデルはOpenAIのWhisperより6.3倍もの高速推論を実現しており、ユーザーが話し終えるのを待たずに同時通訳するデモも披露しています。
従来のシステムでは音声認識に時間がかかったり、発話と応答のあいだにタイムラグが生じたりして「間」が空いていましたが、新技術により会話のテンポが人間同士の場合に近づいています。
音声の自然さ・表現力
ディープラーニングによる音声合成の進歩で、AIの声は飛躍的に自然になりました。後述するElevenLabsの音声モデルは不気味の谷を克服し、「本物の人と電話しているようだ」と言われるほど超リアルな人間らしい声を生成できます。抑揚や間の取り方も滑らかで、従来の機械的な合成音声とは一線を画します。また各社とも感情表現に注力しており、喜怒哀楽のトーンを声に反映したり、相槌や相づちを打ったりすることが可能です。
例えば、「Moshi」と呼ばれるモデルでは音声にリアルタイムで感情を込められる設計がされており、声の抑揚コントロールで共感的なトーンを出すことができます。従来の自動音声は平坦で感情が伝わらないという課題がありましたが、最新AIでは声色や話し方で感情を伝える高度な応答が期待できるのです。
多言語対応と翻訳
グローバル化する顧客対応において、多言語でサービスを提供できるかは大きな課題でした。従来は各言語ごとにオペレーターを配置したり通訳を介したりする必要がありましたが、最新の音声AIは一つのプラットフォームで多数言語をカバーできます。アメリカの音声ユニコーンであるElevenLabsは70以上の言語に対応する統合音声プラットフォームを提供しており、日本語の難しいイントネーションにも対応するべく改良を続けています。
リアルタイム音声翻訳(同時通訳)の技術も向上しており、話者Aの日本語を即座に英語音声で返し、逆方向も対応するといった音声to音声翻訳も視野に入っています。言語の壁をAIで乗り越えることで、例えば日本語しか話せないオペレーターでも英語話者の顧客にリアルタイムで対応できる世界が現実味を帯びています。これは従来の音声ソリューションにはなかった大きな強みです(旧来はそもそも自動翻訳しながら話すことなど不可能でした)。
フルデュプレックス対話
同時双方向の会話を可能にした点も技術的ブレイクスルーです。従来のAI対話はユーザーの発話が終わってから応答を生成するハーフデュプレックス(二者交互)方式でした。そのため、人間同士のように相手の話に相槌を打つことができず不自然さが残っていました。
現在はJ-Moshiという名古屋大学が研究をしているAIモデルがその壁を破り、日本語でもAIが聞きながら相槌や合いの手を入れつつ話すことを実証しています。この技術が実用化されれば、よりストレスのないスムーズな通話体験を顧客に提供できるでしょう。人間のオペレーターとの対話に近い自然な間合いでAIが応対できるようになることが期待できます。
具体的な最新事例
次に、こうした音声AI技術が実際どのように活用されているか、具体的な事例を見てみましょう。ここでは代表的な企業・プロダクトである ElevenLabs, Kotoba Technologies, J-Moshi について、それぞれの導入・活用例や効果をご紹介します。
ElevenLabs(イレブンラボ)
アメリカ発のスタートアップで、わずか創業2年で時価総額33億ドルに達した音声生成AIのユニコーン企業です。高度なディープラーニングモデルによる音声合成を強みとし、テキストからまるで人間が話しているかのように自然な声を生成できます。特に多言語対応とボイスクローン(声質クローン)技術に優れており、70以上の言語で「本人そっくりの声」を作成・読み上げ可能です。
2025年には最新モデル「ElevenLabs v3」を発表し、日本語の読み上げ・対話能力が飛躍的に向上しました。本物の人間と区別がつかないほど自然な音声を実現しており、イントネーションや抑揚、感情まで表現できる点が特徴です。こうした進化により、ElevenLabsは単なる文字読み上げに留まらず、リアルタイム対話にも適用できる音声AIプラットフォームへと発展しており、コールセンターへの適用も視野に入れられています。
ElevenLabsの実用例
ElevenLabsは海外を中心にAI音声エージェントの実用事例が数多く報告されています。例えば米国のスタートアップThoughtly社は、ElevenLabsの音声を組み込んだAIセールス&サポートエージェントサービスを提供しています。このサービスでは受電・架電の両方をAIが行い、予約受付や顧客へのリマインド電話などを自動化しています。驚くべきはその対話の自然さで、実際にThoughtlyを導入したある企業では、AIエージェント(人間の女性の声を模した「ガブリエル」)が電話対応したところ、顧客が後日「ガブリエルさんお願いします」と指名して電話をかけてきたそうです。担当者が不思議に思うほど、顧客はAIを人間のスタッフだと信じて疑わなかったのです。このエピソードは、ElevenLabsの音声生成がいかに人間らしく高品質であるかを物語っています。
出典:Thoughtly、ElevenLabsを活用してAIコールセンターを構築
ElevenLabsのJapan法人も2025年、国内のパートナー企業と共同で日本語特化の高速音声AIエージェント開発に着手しており、日本市場でも高品質なAIコールセンター実現に向けた動きが加速しています。NTTドコモやKDDIグループなど大手もElevenLabsに注目・出資しており、その技術を活用した日本語音声AIソリューション展開が期待されています。
出典:ElevenLabsがSpark+と共同で「コールセンター向け日本語特化音声AI」の開発を開始
Kotoba Technologies(コトバテクノロジーズ)
2023年設立の日本発スタートアップで、リアルタイム音声生成AIの総合技術を開発しています。
日本語を中心に、流暢で自然な音声合成を行う「Kotoba-SpeechGen」をはじめ、エンドツーエンドの音声翻訳(同時通訳)や映像吹き替え、ボイスクローニング、感情表現の反映など多彩な機能を備えています。
さらに超高速の日本語音声認識モデル(OpenAI Whisperの約6.3倍の推論速度)や、日本語⇔英語双方向の音声テキスト翻訳機能も提供しており、日本語音声AIのフロントランナー的存在です。創業から短期間でこれらの技術を次々と形にしており、今後は英語や東南アジア言語への多言語展開も予定しています。
Kotoba Technologiesの実用例
Kotoba Technologiesは創業間もない企業ながら、その技術力で既にいくつかの実証実験・導入が始まっています。一般向けには、同社が公開したリアルタイム音声翻訳(同時通訳)のモバイルアプリが話題になりました。この「同時通訳 – リアルタイム音声翻訳」アプリは、話した内容を瞬時に別の言語に音声変換するもので、公開からわずか3ヶ月でユーザーセッション数が50万回に迫る利用があり、「世界最速レベルのAI同時通訳」としてテレビメディアでも取り上げられました。この成功によりKotobaのリアルタイム音声処理技術の実用性が示されたと言えます。
一方、コールセンター向けの取り組みとして注目なのが、海外系コールセンター企業との実証実験です。同社はすでに多国籍企業とのPoC(概念実証)を進めており、英語をはじめ複数言語での問い合わせ対応ニーズに応えるマルチリンガル音声コミュニケーションシステムの開発に携わっています。
これは、例えば日本語しか話さないオペレーターと英語圏の顧客との間をAIがリアルタイム通訳し、お互い自分の母国語のまま会話できるようにする、といった活用が想定されます。数千人規模でしか存在しないプロの同時通訳者に代わり得る技術として、非常に期待が高まっています。
出典:言語の壁を超える音声生成AI ―― Kotoba Technologiesが描く、グローバルコミュニケーションの未来
J-Moshi(ジェイ・モシ)
こちらは企業ではなく技術モデルの名称ですが、日本のコールセンターへの適用が期待される最新の研究成果です。名古屋大学の研究チームが2025年7月に公開した日本語全二重(フルデュプレックス)音声対話モデルで、ユーザーの発話を「聞きながら同時に応答を話す」ことができます。
J-Moshi最大の特徴は、人間のように相手の話に相槌(あいづち)を打ったり、相手の話を聞きながら合いの手を入れたりできる点です。日本語の自然な会話では「なるほど」「ええ」といった相槌が頻繁に入りますが、従来のAI音声対話はユーザーの発話中は黙って待つしかなく不自然でした。J-Moshiはこれを克服し、「話すこと」と「聞くこと」を両立させた画期的な対話AIです。
わずか4ヶ月で開発され、6万時間を超える日本語音声データで訓練されたこのモデルは、人間の話し方や会話の間合いを捉え、日本語話者が行う相槌まで完璧に模倣しています。さらに、ベースとなった英語モデル「Moshi」はリアルタイムに感情表現も可能な音声AIアシスタントで、J-Moshiも声の抑揚など感情を伴った対話を再現できるポテンシャルがあります。研究段階のモデルながら、日本語の会話AIの新たな地平を切り開く技術として注目されています。
J-Moshiの実用例
J-Moshi自体は研究モデルですが、その公開により日本の音声AI業界全体が刺激を受けています。名古屋大学チームは「J-Moshiなら日本のコールセンターや医療現場、カスタマーサービスで商用利用できる可能性がある」と述べており、今後企業による活用が十分に考えられます。
特に、日本語特有の会話文化(頻繁な相槌や合いの手)に対応できるAIはこれまで存在しなかったため、J-Moshiの登場は画期的です。例えばコールセンターの自動応答にJ-Moshiを組み込めば、顧客が話している途中でも「はい」「承知しました」などと相槌を打ちながら聞き、適切なタイミングで回答する、といった人間顔負けの自然な対話が可能になるでしょう。これはクレーム対応のような繊細な場面でも、顧客に「ちゃんと話を聞いてくれている」という安心感を与える効果が期待できます。
現時点で商用プロダクトとして組み込まれた例はまだありませんが、オープンソースでモデルが公開されているため、国内外のAI企業がこのモデルを基にサービス開発を進める可能性があります。
J-Moshiの技術コンセプトはElevenLabsやKotobaとも補完的であり、例えばElevenLabsの高品質な声でJ-Moshi的な全二重会話をする、といった組み合わせが実現すれば鬼に金棒です。日本語のコールセンターAIが一気に「おもてなし」レベルのきめ細かい対話力を持つ未来も、そう遠くないかもしれません。
出典:デモサイト:日本語Full-duplex音声対話システムの試作
Open AI(Realtime API) ※2025/10 追記
OpenAI Realtime API は、テキストを中心とした従来の API を拡張し、音声やマルチモーダルをリアルタイムに扱えるように設計された新しいインターフェースです。これまで音声アプリケーションを構築する場合、音声認識(ASR)、テキスト処理(LLM)、音声合成(TTS)を別々に組み合わせる必要がありましたが、Realtime API はこれらを統合することで、遅延の少ない自然な会話体験を実現しています。
技術的な特徴として、まず双方向通信を可能にする WebSocket を用いたストリーミング接続が挙げられます。これにより、HTTP のようにリクエストとレスポンスを逐次やりとりする方式では難しかった「会話の途中で返答する」「相手の話に割り込む」といった人間らしいやりとりが可能になります。また、生成中の応答を部分的にストリームで送信できるため、ユーザーの発話が終わるのを待たずに返答を始めることもできます。
さらに、音声入力から音声出力までを一気通貫で処理する構成になっているため、従来のような複数の変換ステップによる遅延やニュアンスの損失が少なくなっています。発話の途中で割り込みがあった場合にも対応できるよう、内部的に会話状態の管理や発話終了検知の仕組みを持っており、自然なターンテイキングが可能です。関数呼び出し機能との統合も進んでおり、音声対話中に天気情報を取得したり、予約システムと連携したりといった外部 API との連携もスムーズに行えます。また、SIP(Session Initiation Protocol)をサポートしている点も特徴的で、企業の PBX や電話回線と直接接続できるため、AI 音声ボットや自動応答システムの構築にも向いています。
今後予測される技術的進化の方向性
音声AI技術は今後ますます進化し、より高度な機能を備えていくと予想されます。ここでは、特に注目される技術的トレンドをいくつか挙げてみます。
感情理解・感情に応じた対応
現在も簡単な感情分析は行えますが、今後は顧客の声のトーンや話の内容から微妙な感情をリアルタイムに読み取り、それに応じた対応や話し方を変える技術が発展するとみられます。例えば、顧客が苛立っていると判断したらAIエージェントの声色をより落ち着いたトーンに変えたり、謝罪の言葉を増やしたりする、といった適応が可能になるでしょう。
実際にElevenLabsのロードマップでも「音声感情認識の向上」に取り組むとされています。顧客の感情に寄り添うAIは、より人間らしく信頼感のある対応に繋がるはずです。
▼AIの感情理解や感情分析に関する記事はこちらもご覧ください
【技術解説】対話型AIの進化と感情理解技術の最前線。AIエージェントによる感情対応は可能か。
感情分析とは?活用メリットやコールセンターで注目される背景を解説
マルチモーダル・多言語対応の深化
現状でも多言語に対応する音声AIはありますが、将来的には一つのAIエージェントが複数言語を自在に切り替え、必要に応じてリアルタイム翻訳も行うのが当たり前になるでしょう。Kotobaが進める音声同時通訳技術などはその先駆けと言えます。
さらに音声だけでなく、テキストチャットや画像・動画の情報まで統合して理解・応答するマルチモーダルな対話AIへの発展も考えられます。将来のコンタクトセンターAIは、電話の声だけでなく、メールやチャット、顧客の表情(ビデオ通話の場合)まで分析し、総合的に判断して対応を最適化するかもしれません。
より軽量で専用性の高いモデルの普及
現在は巨大な汎用音声モデルが主流ですが、今後は用途特化型の小型言語モデル(SLM)の活用も増えるでしょう。実際、日本語のコールセンター向けには小型で高速な音声対話モデルを組み込む動きがあり、限定されたドメインであれば小さなモデルでも高精度に動作するメリットがあります。
モデルが軽量化すればオンプレミスやエッジデバイスで動かすことも容易になり、セキュリティやプライバシー面でオンサイト処理を求めるコールセンターにも導入しやすくなります。クラウドに頼らない自律型AIエージェントなども登場するかもしれません。
これら以外にも、音声AI分野は日進月歩で新しい試みが出てきています。より人間に近いコミュニケーションを実現するための研究開発が今後も加速していくことは間違いありません。コールセンター向け音声AIは、技術の進化とともにますます高度化し、その導入メリットも大きく広がっていくでしょう。
音声AIがコールセンター業界に与えるインパクト
最後に、こうした音声AI技術の普及がコールセンター業界にもたらす影響についてまとめます。すでに触れたように、AI音声エージェントの導入は業務効率の向上や顧客体験の改善に寄与していますが、それに伴いオペレーターの役割や働き方にも変化が現れ始めています。
業務効率の劇的向上とコスト削減
AIエージェントは人間に比べて圧倒的に高速かつ並列に業務を処理できます。待ち呼(保留)や折り返し対応が減り、顧客の待ち時間は大幅に短縮します。さらにAIは24時間365日休まず稼働できるため、人員を増やさずとも夜間や週末の問い合わせに対応可能です。
人手不足が叫ばれる業界において、少ない人員でより多くの問い合わせを捌ける意義は大きく、人件費削減やアウトソーシング費用の圧縮といったコスト面のメリットも期待できます。
顧客満足度・CX(カスタマーエクスペリエンス)の向上
音声AIの導入により、顧客体験(CX)は向上するというデータが出始めています。例えば、LINEWORKS 社が提供している「LINEWORKS AiCall」を導入し、TNPS調査でスコアが向上したという報告もあります。(参照:https://line-works.com/cases-ai/zurich/)
AIによって待たされない・いつでもつながる・正確な回答が得られるとなれば、顧客にとってこれ以上ない利便性です。加えて、最近のAI音声は声質も丁寧で共感的に話すため、多くの顧客は機械と感じないままストレスなく用件を済ませられます。
さらに対応履歴や嗜好をAIが蓄積・学習し、個々の顧客に合わせたパーソナライズ対応が可能になれば、顧客ロイヤルティ向上にもつながります。音声AIは単なるコスト削減策ではなく、顧客サービス品質を底上げするツールとしての位置付けを強めています。
オペレーターの役割変化と働き方改革
音声AIの台頭で「AIが人間の仕事を奪うのでは」との声もありますが、現実には人間オペレーターの役割シフトとして現れる可能性が高いです。AIがルーチンで単調な問い合わせや簡易なFAQ対応を肩代わりすることで、人間のスタッフはより付加価値の高い業務に注力できるようになります。
AIと人間の協働が進めば、オペレーターの仕事はクレーム対応や複雑な問題解決、感情的ケアが必要なケースなど、人間ならではの対応が求められる場面にシフトしていくでしょう。またAIエージェントを監督・トレーニングする新たな業務も生まれ、オペレーターはAIを扱うスーパーバイザー的な役割も担うようになるかもしれません。結果的に、単調で精神的負担の大きい業務から解放され、人間ならではの創造性や共感力を発揮できる業務にフォーカスできるようになることが理想的な姿と言えます。
まとめ
音声AI技術は、ElevenLabs、Kotoba Technologies、J-Moshiなどの革新的な取り組みにより、従来のコールセンター業界の常識を大きく変えようとしています。リアルタイム性、自然な音声表現、柔軟な対話理解、多言語対応、そしてフルデュプレックス対話といった技術革新により、AIエージェントは人間のオペレーターに匹敵する、あるいはそれを上回る対応品質を実現しつつあります。
一方で、人間のオペレーターの役割も単純な置き換えではなく、より高度で創造的な業務へのシフトが期待されます。AIとの協働により、人間ならではの共感力や問題解決能力を活かせる環境が整うことで、働く人々にとってもより充実した職場環境の実現が可能になるでしょう。
音声AI技術はまだ発展途上にありますが、その可能性は計り知れません。今後数年間で、私たちが想像する以上に自然で高品質なAI音声エージェントが当たり前の存在となり、コールセンター業界のみならず、あらゆる顧客接点における新たなスタンダードを築いていくことが予想されます。企業にとっては、この技術革新の波に早期に対応し、適切に活用することが競争優位性の確保につながる重要な戦略となるでしょう。
業務効率化や人手不足のお悩み、AI×BPOで解決しませんか?
「業務の生産性を上げたい」「少人数でも高品質な対応を実現したい」そんなご要望はありませんか?
ウィルオブ・ワークでは、BPOサービスを通じた業務支援に加え、AIと人のハイブリッド型BPO(AI-BPO)の導入支援も行っています。
お客様の業務内容や体制に応じて、最適な改善策をご提案いたします。
Writer編集者情報
-

コネナビ編集部 平井 美穂
2012年、株式会社セントメディア(現:株式会社ウィルオブ・ワーク)へ入社。
コールセンターとオフィスワーク領域に特化した人材サービスに従事し、カスタマーサポートをはじめ、営業やキャリアアドバイザーなど幅広い職務を経験。
現場で培ったCS対応力と人材支援の知見を軸に、採用や運営における課題解決を支援。
2022年からは、コンタクトセンター業界の情報サイト「コネナビ」編集部の責任者として、業界の課題に寄り添う情報発信を推進。
企業向けメディア「コネナビ」と求職者向けメディア「コネワク」を通じて、ユーザーの課題解決と業界の成長に貢献することを目指している。
趣味: 森林浴、神社巡り、アートに触れること
特技: 細かい点に気づくこと